- TOP
- 企業向けColumn
- 女性の健康課題とは?社会の取り組みや女性活躍の未来
女性の健康課題とは?社会の取り組みや女性活躍の未来

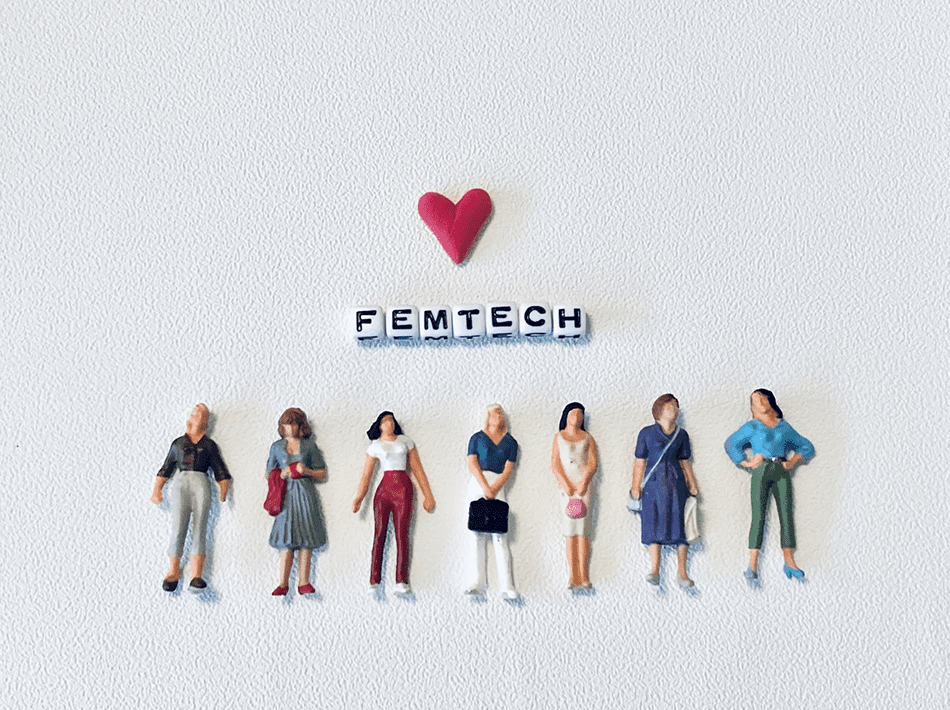
女性の健康にはさまざまな課題が含まれます。例えば、生理痛(月経痛)やPMS(月経前症候群)、更年期症状といった身体的な問題があります。また、子育てと仕事の両立など、日常生活の中で直面する悩みも少なくありません。
本記事では、女性の健康課題を取り巻く現状と、それに対する社会の取り組み、そして未来への展望について詳しく解説します。
女性の健康課題とは
女性はそれぞれのライフステージで妊娠・出産、ホルモンバランスの変化、更年期症状などによる、女性特有の健康課題を抱える可能性があります。
これらの健康課題は、日常生活や仕事に大きな影響を及ぼすことがあります。
生理痛(月経痛)、PMS、更年期症状など
多くの女性が経験する可能性がある、生理痛(月経痛)やPMS、そして加齢に伴う更年期症状は、身体的にも精神的にも負担が非常に大きいものです。
生理痛(月経痛)では、腹痛や頭痛、全身のだるさなどの症状を認め、仕事や日常の生活に様々な影響を与えます。また、PMSでは、気分の浮き沈みや集中力の低下などの精神的な症状を認めることもあり、こちらも仕事や日常の生活へのさまざまな影響が出現します。
更年期症状は、加齢に伴うホルモンバランスの変化によって引き起こされる身体や心の不調です。ほてりや発汗、不眠、イライラなどの症状が現れることがあります。これらの不調は、働く女性のパフォーマンスに影響を与え、生産性の低下につながる可能性があるでしょう。
子育てと仕事の両立
近年、両親と子どもだけで構成される核家族が増え、出産後に子育てと仕事を両立する必要がある女性が多くなっています。仕事と家庭の両方の役割を果たすことは、大きな負担となり、心身へ大きな影響を与えます。
特に、仕事のストレスに育児の負担が重なると、睡眠不足や慢性的な疲労などから健康上の問題を引き起こすこともあるでしょう。
性の健康
WHOの定義によると、性の健康は、身体的、感情的、精神的、社会的なウェルビーイングの重要な要素であり、単に病気や障害がないことではありません。特に女性の健康課題については、性差に基づいた取り組みが十分でなかった歴史があります。
男性と女性では、罹患しやすい病気やその症状、治療法に違いが見られるため、性差を考慮したアプローチが必要です。特に女性に関しては、ホルモンの変動やライフステージごとの変化が健康に深く影響します。月経や妊娠、出産だけでなく、精神的な健康、社会的な役割とのバランスといった多角的な側面に目を向ける必要があります。
これらの健康課題に向き合い、性の健康を守るためには、性差を踏まえた包括的な視点が不可欠です。
女性の健康課題に対する社会の取り組み
こうした女性の健康課題に対し、政府や医療機関、企業などがさまざまな対策を講じています。
政府の政策
経済産業省では、参加費無料で性別関係なく長く健康に働ける職場環境の整備を推進するため、「健康経営における女性の健康施策効果検証プロジェクト」を実施しています。企業が女性の健康に関する取り組みを進め、その効果を客観的に測定し、フィードバックを提供することで、より良い健康施策の実現を支援します。
また、厚生労働省は女性の健康を守るため、女性特有の健康課題に関する調査研究を推進し、その成果を広く普及・活用することを目的に研究事業を立ち上げました。性感染症対策の効果検証や、ライフステージごとの健康課題の調査など、女性特有の課題に対応する研究を進めています。
さらに、国民の健康を総合的に推進するための健康づくり運動である健康日本21(第3次)では、女性特有の健康課題に焦点を当て取り組むために、男性と女性の性差に着目し、特に女性の健康問題について検証することの重要性ついて明示しています。
医療機関の取り組み
女性の健康課題に対する社会全体の取り組みとして、医療機関も重要な役割を果たしています。
例えば、国立の医療研究機関では、女性特有の健康課題に対して幅広い研究や支援が行われています。妊娠・出産に伴う健康問題や思春期、更年期における身体的・精神的な変化への対応、性感染症対策の効果検証など、多岐にわたるテーマが対象です。これらの研究の多くは、厚生労働省や文部科学省などの助成を受けて進められており、得られた成果は国内外の医療現場や政策立案に活用されています。
こうした医療機関の取り組みは、社会全体の健康意識の向上や具体的な課題解決に向けた重要な一歩となっています。
民間の取り組み
ここでは、東京都産業労働局が優良企業として紹介している運送会社の取り組みについて紹介します。
こちらの会社では、女性社員のみではなく男性社員も含めて年1回すべての従業員に向けて、女性の健康への理解と関心を深める研修を実施しています。同じ課題意識を持つ中小企業と合同で産業医を選任し、健康課題に対するアドバイスや研修を受けている運送会社です。
健康経営を取り入れたことによって、新入社員の志望動機の9割が「健康経営に魅力を感じている」と回答しました。他職種からの転職も増加し、健康経営が人材確保につながっています。
出典:「働く女性のウェルネス向上委員会」(東京都産業労働局)(2025年1月13日利用)
女性の健康課題解決に向けた未来の展望
女性の健康課題を解決するために、今後さらなる技術革新や社会意識の変化が期待されています。
医療技術の発展
女性の健康課題解決に向けて、フェムテック(Femtech)の分野では、デジタルヘルス技術やAIを活用した診断支援、不妊治療、更年期ケアに関連する医療技術の発展が期待されています。これらの取り組みは、様々な研究機関での研究が進められています。これらの技術は、女性のライフステージごとの健康課題の解決に寄与するでしょう。
社会意識の変化
国や地方自治体だけでなく、一般企業でも女性の健康に対する取り組みが進んでいます。社会全体が健康課題への理解を深めることで、女性が働きやすい環境が実現します。そのためには、いくつかの意識の変化が求められます。
例えば、生理痛(月経痛)やPMS、更年期症状などの健康課題を「個人の問題」とせず、職場全体で配慮する姿勢が必要です。また、これらを理由に女性の能力や意欲を低く見積もるような偏見も解消していくべきです。
こうした意識の広がりが、性別を問わず健康を尊重する社会づくりにつながるでしょう。
女性のエンパワーメント
女性のエンパワーメントとは「女性が自分自身の人生を決定する権利と能力を持ち、社会や経済、政治などのさまざまな分野で活躍できること」を意味しています。
2010年3月に、国連と企業の自主的な盟約の枠組みである国連グローバル・コンパクト(GC)と国連婦人開発基金(UNIFEM)(現UN Women)が、共同で「女性のエンパワーメント原則(WEPs)」を提唱しました。この7原則は、企業がジェンダー平等と女性のエンパワーメントを推進し、職場や社会での平等と多様性を実現するための具体的なガイドラインとなっています。
- 1)トップのリーダーシップによるジェンダー平等の促進
- 2)機会の均等、インクルージョン、差別の撤廃
- 3)健康、安全、暴力の撤廃
- 4)教育と研修
- 5)事業開発、サプライチェーン、マーケティング活動
- 6)地域におけるリーダーシップと参画
- 7)透明性、成果の測定、報告
出典:「女性のエンパワーメント原則(WEPs)」(内閣府)(2024年1月13日利用)
女性の社会での活躍が進むことで、経済の活性化に大きく貢献すると期待されています。
フェムテックが切り拓く女性の健康課題の解決
「フェムテック」は、女性が抱く健康上やライフスタイルの悩みを解決する商品やサービスのことを指します。女性(Female)とテクノロジー(Technology)をかけ合わせてその名前Femtechが付けられました。
フェムテックの市場は急速に拡大しており、女性の健康課題を解決するテクノロジーが次々に登場しています。
例えば、月経周期をリアルタイムで把握ができるスマートウェアラブルデバイスや、不妊治療を支援するアプリなどがあります。これらの技術は、自分の体を理解し、健康的な選択をサポートする有用なツールです。
まとめ
女性の健康課題は、生理痛(月経痛)や更年期症状といった身体的な問題から、子育てと仕事の両立、性の健康に至るまで、多岐にわたる課題があります。
現在、政府や医療機関、民間企業が連携し、女性がより健康的で活躍しやすい社会を目指す取り組みが進んでいます。
さらに、医療技術の発展やフェムテックの普及が、これまで解決が難しかった課題を新たな形で解決する可能性を秘めています。
女性の健康が守られ、社会での活躍がさらに進む未来を実現するために、私たち一人ひとりができることを考え、行動していくことが求められています。
監修者

大迫 鑑顕
千葉大学大学院医学研究院精神医学 特任助教
Bellvitge University Hospital, Barcelona, Spain
医学博士、精神保健指定医、日本精神神経学会認定精神科専門医・指導医、日本医師会認定産業医、公認心理師
あすか製薬 フェムナレッジでは、女性従業員の活躍を推進するサービスを導入したい企業の皆さまや今後女性特有の健康課題に関する取り組みを検討されている企業の皆さま向けに動画研修サービスをご提供しております。
Mint+ フェムナレッジについての
お問い合わせはこちらから


