- TOP
- 企業向けColumn
- メンタル不調の原因や症状、職場での対応について知りたい
メンタル不調の原因や症状、職場での対応について知りたい

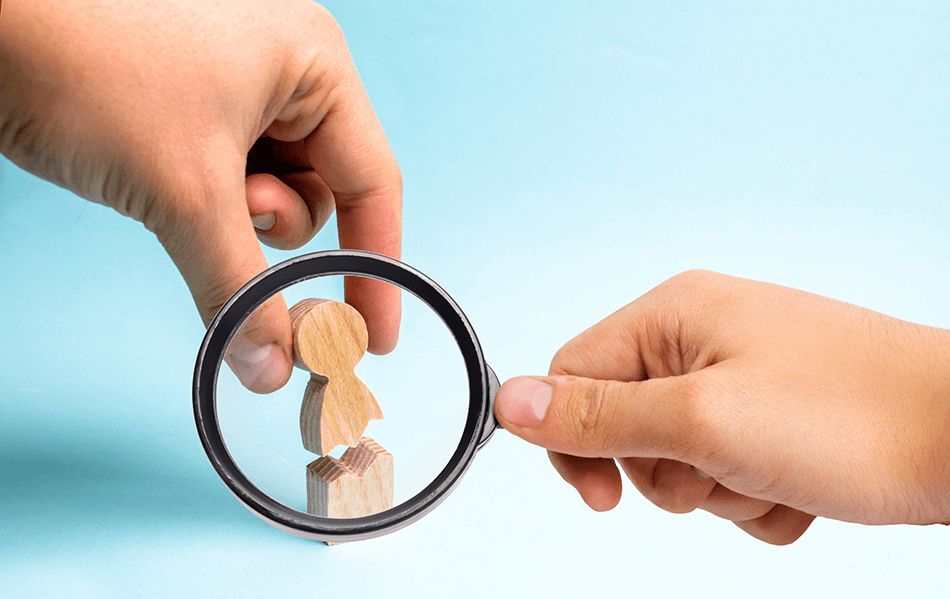
現代のビジネス環境では、多くの人がストレスを抱えながら働いています。メンタル不調が進行すると、集中力の低下や業務ミスの増加、最悪の場合は休職や離職につながることもあります。企業としても、従業員のメンタルヘルスを守ることは重要な課題です。
本記事では、メンタル不調の主な原因、症状、そして企業ができる対応策について詳しく解説します。
メンタル不調の主な原因とは
メンタルヘルスの不調とは、厚生労働省による「労働者の心の健康保持増進のための指針」によると、「精神および行動の障害に分類される精神障害や自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身の健康、社会生活および生活の質に影響を与える可能性のある精神的および行動上の問題を幅広く含むもの」と定義されています。つまり、単に精神疾患のみならず、心身の健康や生活の質に影響を及ぼす精神的な問題全般を指します。
出典:セルフメンタルヘルス(厚生労働省)(2025年3月7日利用)
メンタルの不調は、1つではなく、さまざまな要因が絡み合って発生することが多いです。大きく分けると、心理的要因、環境的要因、個人的要因の3つに分類できます。
心理的要因
普段生活をしていると、さまざまな心理的なストレスを感じることがあります。例えば職場では、上司や同僚との人間関係、過度な責任感、業績へのプレッシャーなどが考えられます。さらに、職場の人間関係が悪いと、日常的にストレスを感じやすくなるでしょう。
プライベートでのストレスの要因としては、夫婦関係、親子関係、ご近所付き合いなどが挙げられます。仕事から帰宅しても夫婦関係が良好でないと、心が休まる時間が少なく、ストレスを感じやすくなります。
環境的要因
職場環境そのものも、メンタル不調の原因となります。代表的なものとして、長時間労働、過重労働、職場の雰囲気の悪さなどがあります。
長時間労働が常態化している職場では、心身の疲労が蓄積しやすくなります。十分な休息を取れないまま働き続けると、気持ちの余裕がなくなり、ストレス耐性も低下してしまうでしょう。
厚生労働省によると、時間外労働や休日労働の時間が月100時間を超えたり、2~6ヶ月の平均が月80時間を超えたりすると、健康障害のリスクが高まるとされ、月45時間以内であれば、健康障害のリスクは比較的低いとされていますが、これには個人差があることにも留意する必要があります。
出典: 過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ(厚生労働省)(2025年3月7日利用)
個人的要因
メンタル不調には、個人の性格や生活習慣も影響します。
例えば、睡眠不足や不規則な食生活、運動不足、自尊心の低下などは、ストレス耐性を低下させる要因となります。親しい人との別れなど、誰もが経験するライフイベントでも、その受け止め方によってストレスの感じ方は異なります。このように、ストレスの影響の大きさは、個人の性格や生活習慣によっても変わるのです。
メンタル不調の症状とは
メンタル不調の症状は、精神的なものだけでなく、身体的な症状や行動の変化としても現れます。これらは相互に影響し合い、悪化すると仕事や日常生活にも支障をきたします。
精神的症状
メンタル不調の代表的な精神的症状には、以下のようなものがあります。
- 気分が沈み、やる気が起きない
- 不安な気持ちになる
- イライラしやすく、怒りっぽくなる
- 集中力が続かず、物事に興味が持てなくなる
身体的症状
メンタルの不調に関連した身体的な症状には、以下のようなものがあります。
- 全身が重だるく、疲労感が抜けない
- 動悸やめまいが起こる
- 頭痛がする
- 夜眠れない、不眠が続く
- 食欲が低下する、または逆に食べ過ぎてしまう
ストレスが続くと、自律神経のバランスが崩れ、さまざまな身体症状として現れます。
行動の変化
精神的・身体的症状が現れると、次第に行動にも変化が現れます。
- 精神的な不調が続くと、外に出るのが億劫になり、引きこもりがちになる
- 物事に対してやる気が起こらず、生活習慣が乱れる
- 全身のだるさや疲労が抜けず、早退や遅刻、ミスやクレームにつながる
- 怒りっぽくなり、イライラが続くことで、職場や家庭での人間関係が悪化する
これらの変化に早く気づくことで、メンタル不調を悪化させる前に適切な対応をとることができます。
従業員の心の健康を守るために
メンタル不調を未然に防ぎ、従業員が安心して働ける環境を整えることは、企業にとって重要な課題です。企業が従業員のメンタルヘルスを支援するためには、研修や制度の整備、環境の改善、復帰支援の仕組みなど、包括的な対策が求められます。
以下に、具体的な取り組みを紹介します。
メンタルヘルス研修の導入
従業員が自分自身のストレスと向き合い、適切に対処できるようにするためには、メンタルヘルス研修が効果的な手段の一つです。職場でよく見られるストレス要因や対処法を学ぶことで、早期にセルフケアを行えるようになります。
厚生労働省の提供する「こころの耳」では、eラーニングでメンタルヘルスについて学べるように情報を提供しています。
また、管理職向けの研修も重要です。管理職は、部下のメンタル不調に気づき、適切に対応する役割を担っています。しかし、「どのように声をかけたらよいのか分からない」「部下のプライバシーを尊重しつつ、支援する方法が分からない」と悩む上司も少なくありません。研修を通じて、適切なコミュニケーションスキルや支援方法を学ぶことが、職場全体のメンタルヘルス向上につながります。
ストレスチェック制度の活用
ストレスチェック制度は、従業員のストレス状態を定期的に把握し、メンタル不調を未然に防ぐための仕組みです。平成27年12月に施行され、企業に義務化された制度ですが、ただ実施するだけではなく、結果を活用した職場改善が重要となります。
ストレスレベルが高いと判断された方には、産業医やカウンセラーとの面談機会を提供し、状況に応じて勤務状況の調整を行うことが必要です。また、職場全体の傾向を分析し、ストレス要因を特定することで、組織の全体的な効率化にもつなげることができるでしょう。
職場環境の改善
メンタルヘルス対策の基本は、従業員がストレスを感じにくい職場環境を整えることです。
長時間労働は従業員の健康被害を引き起こす要因になるため、適切な労働時間の管理や休憩時間の確保は従業員のメンタルヘルスにとって重要になるでしょう。その準備として、労働時間を正確に把握するために、本人認証が必要な勤怠管理システムの導入なども一つの手段となるでしょう。
その他にも、相談しやすい環境を整えるために、産業医や保健師を配置しメンタルヘルスに対する相談を受け付ける窓口を開設するといった方法も効果的です。
その他に、近年注目されているのがフェムテック(Femtech)サービスの導入です。フェムテックは、女性の健康課題をサポートするテクノロジーやサービスを指します。
例えば生理痛(月経痛)やPMS(月経前症候群)、更年期症状などに配慮し、職場に婦人科オンライン相談サービスを導入する、生理休暇の取得を促進し、気軽に利用できる仕組みを作る、オフィス内にフェムテック製品(温熱パッド、ナプキンなど)を設置することなどが挙げられます。
女性従業員の働きやすさを向上させることは、組織全体のメンタルヘルス向上にもつながります。男女問わず、健康とパフォーマンスを最大限に発揮できる職場環境を整えることが重要です。
職場復帰支援プログラムの構築
メンタル不調で休職した従業員が、スムーズに職場復帰できるようにするためには、職場復帰支援プログラムが必要です。休職中に体調が改善していたとしても、仕事をしている際とは生活リズムも異なるため、復帰を急かしてしまうとメンタルヘルスの問題が再発するリスクが高まります。そのため、段階的に業務を再開できる仕組みを整えることが重要となります。
厚生労働省によると、一般的な職場復帰支援のステップは
- 1.病気休業の開始および休業中のケア
- 2.主治医による職場復帰の判断
- 3.職場復帰の可否の判断および職場復帰支援プランの作成
- 4.最終的な職場復帰の決定
- 5.職場復帰後のフォローアップ
の流れで進みます。
出典:心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(厚生労働省)(2025年3月7日利用)
従業員のメンタルヘルスを守ることは、企業にとっても大きなメリットがあります。
研修や制度の整備、職場環境の改善、復職支援など、包括的な対策を講じることで、働きやすい職場を実現できるでしょう。
まとめ
メンタル不調の原因はさまざまであり、企業として適切な対応をすることで、従業員の健康を守り、働きやすい環境をつくることが重要です。
また近年注目されているフェムテックサービスを導入することで、女性従業員の働きやすさを向上させることができます。
この機会に従業員のメンタルヘルスを守る対策を考えてみませんか。
監修者

大迫 鑑顕
千葉大学大学院医学研究院精神医学 特任助教
Bellvitge University Hospital, Barcelona, Spain
医学博士、精神保健指定医、日本精神神経学会認定精神科専門医・指導医、日本医師会認定産業医、公認心理師
あすか製薬 フェムナレッジでは、女性従業員の活躍を推進するサービスを導入したい企業の皆さまや今後女性特有の健康課題に関する取り組みを検討されている企業の皆さま向けに動画研修サービスをご提供しております。
Mint+ フェムナレッジについての
お問い合わせはこちらから


