- TOP
- 企業向けColumn
- メンタルヘルスのラインケアとは?必要性や企業における重要性について
メンタルヘルスのラインケアとは?必要性や企業における重要性について

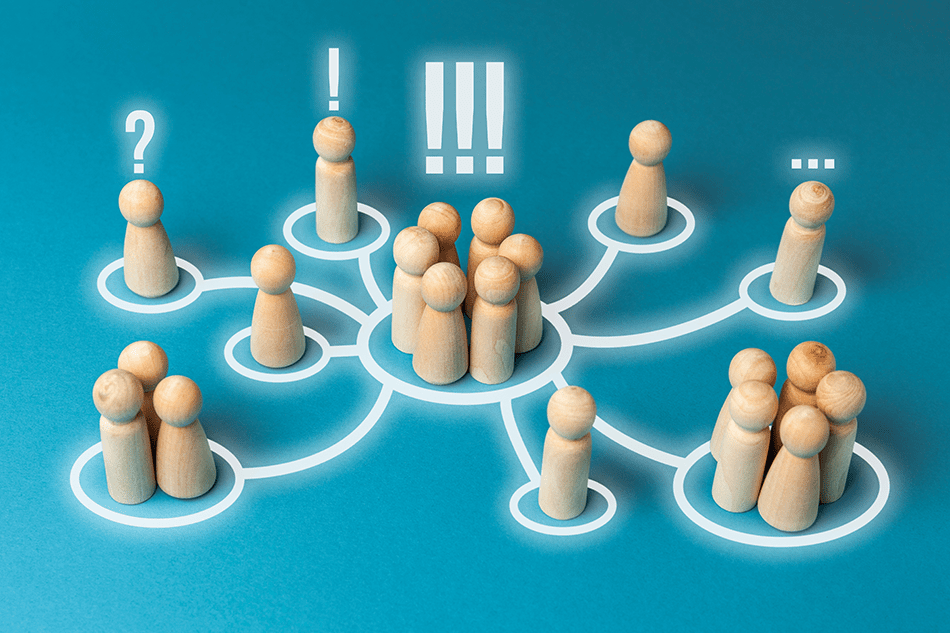
メンタルヘルスの不調による労働人口の低下や生産性の低下を受けて、厚生労働省では「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を策定し、その中で4つのケアを重要視しています。そのうちの1つがラインケアです。
出典: 職場における心の健康づくり(厚生労働省)(2025年2月12日利用)
しかし、ラインケアという言葉には、あまり馴染みがない方もいるかもしれません。本記事では、ラインケアについて詳しく解説します。
ラインケアとは?
ラインケアとは、働く方々の心の健康の保持増進のための指針において重要視されているケアの一つです。ラインケアの定義や位置づけを詳しく見ていきましょう。
ラインケアの定義
ラインケアは「日頃の職場環境の把握と改善、部下の相談対応など管理監督者が行うケア」と定義されています。
ラインケアとして行うべき事柄は次の通りです。
- 部下の事例性の把握
- 職場の環境改善
- 部下に対する相談
- 産業保健スタッフとの連携
精神的な不調は自分自身で気づけないケースもあったり、気付いていても対処法が分からずに過ごしたりするケースがあります。ラインケアでは管理監督者が、働く方々の不調に気づき、適切な対応をすることが重要視されています。
メンタルヘルスの4つのケアとは
冒頭でも紹介した通り、ラインケアは「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の4つのケアのうちの一つです。メンタルヘルスの4つのケアは次の通りです。
- セルフケア
- ラインケア
- 事業場内産業保健スタッフ等によるケア
- 事業場外資源によるケア
セルフケアとは、名前の通り、自分の不調に自分で気づき適切なケアをすることです。
一方、事業場内産業保健スタッフ等によるケアは、企業内にいる産業医や保健師、衛生管理者などで行われるケアです。
また、事業場外資源とは医療機関などの専門機関のことを言います。
メンタルヘルスケアは自分でケアをすることからスタートし、さまざまな職種や資源と連携しながらケアを進めていくことが必要となるのです。
メンタルヘルス対策におけるラインケアの位置づけ
メンタルヘルス対策において、ラインケアは重要な役割を果たします。職場で生じるメンタルヘルス不調は、職場環境の改善なしには根本的な解決が難しいためです。
ラインケアは、労働契約法や労働安全衛生法に基づく安全配慮義務の一環として位置づけられています。特に、管理監督者をはじめとする職場の上位者は、その権限と責任に応じて安全配慮義務を果たすことが求められます。
なぜラインケアが必要なのか?
ラインケアは企業においてさまざまなメリットをもたらすことも分かっています。ここからは、ラインケアが必要とされる理由について解説します。
職場におけるメンタルヘルス問題
職場でのメンタルヘルスの課題は、従業員の健康だけでなく、企業全体の持続的な成長にも大きく関わる重要な問題です。
厚生労働省によると、メンタルヘルスの不調によるうつ病患者は40~50代と働き盛りの世代に多い傾向にあります。
出典: ラインケアについて~気づき・声がけ・対応を中心に~(全国健康保険協会)(2025年2月12日利用)
これにより企業の生産性や職場環境にも影響が及ぶことが懸念されています。
ラインケアが企業にもたらすメリット
ラインケアの導入は、従業員の健康を守り、働きやすい職場環境をつくる上で非常に重要です。メンタルヘルスの問題が早期に発見・対応されることで、従業員が安心して働き続けることができ、結果として職場全体のパフォーマンス向上につながることが期待できます。
企業にとっても安定した人材確保と生産性の向上が期待できます。このように、ラインケアは従業員の健康と企業の持続的な成長の両面において、大きなメリットをもたらします。
ラインケアを怠ることによるリスク
管理監督者の中には、メンタルヘルスの不調を個人の問題と捉え、ラインケアを軽視するケースがあります。しかし、適切なラインケアを行わないことで、従業員の離職や企業の損失を招くだけでなく、メンタルヘルス不調が労働災害として認定され、訴訟に発展する可能性もあります。
実際に、適切なケアが行われず従業員に深刻なメンタルヘルスの問題が発生し、自殺等の問題に発展したケースで、企業側の責任が認められた事例も報告されています。訴訟に発展すれば、企業のイメージダウンにつながるほか、敗訴した際には多額の賠償金を支払う必要もあることから、ラインケアを怠ることは、企業にとって大きなリスクとなるのです。
ラインケアの具体的な実施方法
ラインケアは重要ですが、管理監督者だけに任せるのは負担が大きく、適切な対応が難しい場合もあります。そこで、ここからは具体的な実施方法について解説します。
実際のラインケアの流れ
実際のラインケアのファーストステップとして必要なことは、部下の「いつもと違う」という異変に気付くことです。
自ら状況を説明できる人もいますが、信頼関係が築かれていない場合、こちらから声をかけても自身の状況を打ち明けられないことがあります。そのような場合は、職場の産業医、保健師、看護師、心理相談担当者、産業カウンセラー、または臨床心理士と連携し、状況を把握したうえで適切な対応を検討しましょう。また、得た個人情報には十分配慮することが重要です。
治療に専念するために休職に入った場合には、スムーズに復職できるように職場環境を整えることが必要です。
ラインケアの事例
ラインケアをどのように行っていくべきか悩む方にむけて、具体的な事例を紹介します。
多くの事業所がまず取り組んでいるのは、メンタルヘルスに関する知識の普及です。特に管理職世代の中には、メンタルヘルスへの理解が不十分な時代を生きてこられた方々もいらっしゃるため、研修や勉強会を通じてその重要性を伝え、メンタルヘルスをより身近に感じてもらう取り組みが行われています。
しかし、管理職自身がラインケアに適切に対応できるか不安を抱えるケースもあります。そこで、一部の事業所では、管理職を中心としたメンタルヘルス専門の部署を設置し、管理職や事業場内の産業保健スタッフを配置することで、ラインケアの次のステップへと円滑につなげられるような仕組みを整えました。
企業規模を問わず、多くの企業がラインケアに取り組んでおり、特に管理職への負担を軽減しながら実施できるような工夫がなされています。
フェムテックを活用した職場環境の整備
職場環境の整備にフェムテックを活用する事業所が増えています。あわせて、女性のメンタルヘルスやウェルビーイングの向上を目的としたフェムテック関連サービスを開発する企業も増加しています。
特に女性のメンタルヘルスを可視化できるツールが増えているため、アプリを利用して生理(月経)周期などと併せて自身のメンタルの変化を可視化したり、必要によってはオンライン診療を活用したりといった方法があります。
フェムテックの活用は、女性が働きやすい職場環境の整備へとつながるでしょう。
まとめ
職場や仕事で受けたストレスを適切に評価し、職場環境を整えるラインケアは、結果的に企業の利益にも影響を与えます。一方で、管理職が適切にラインケアを実施できるか不安を感じることも少なくありません。
こうした不安を解消し、管理職が適切にラインケアを実施できるように、事業場内の産業保健スタッフと連携して取り組む事業所も増えています。
労働人口や生産人口を維持しながら企業の利益を向上させるためにも、ラインケアに注目してみましょう。また、女性へのラインケアの一環として、フェムテックの活用もぜひご検討ください。
監修者

大迫 鑑顕
千葉大学大学院医学研究院精神医学 特任助教
Bellvitge University Hospital, Barcelona, Spain
医学博士、精神保健指定医、日本精神神経学会認定精神科専門医・指導医、日本医師会認定産業医、公認心理師
あすか製薬 フェムナレッジでは、女性従業員の活躍を推進するサービスを導入したい企業の皆さまや今後女性特有の健康課題に関する取り組みを検討されている企業の皆さま向けに動画研修サービスをご提供しております。
Mint+ フェムナレッジについての
お問い合わせはこちらから


