- TOP
- 企業向けColumn
- メンタルヘルスのセルフケアとは?会社や自宅でできるリフレッシュ方法5つ
メンタルヘルスのセルフケアとは?会社や自宅でできるリフレッシュ方法5つ

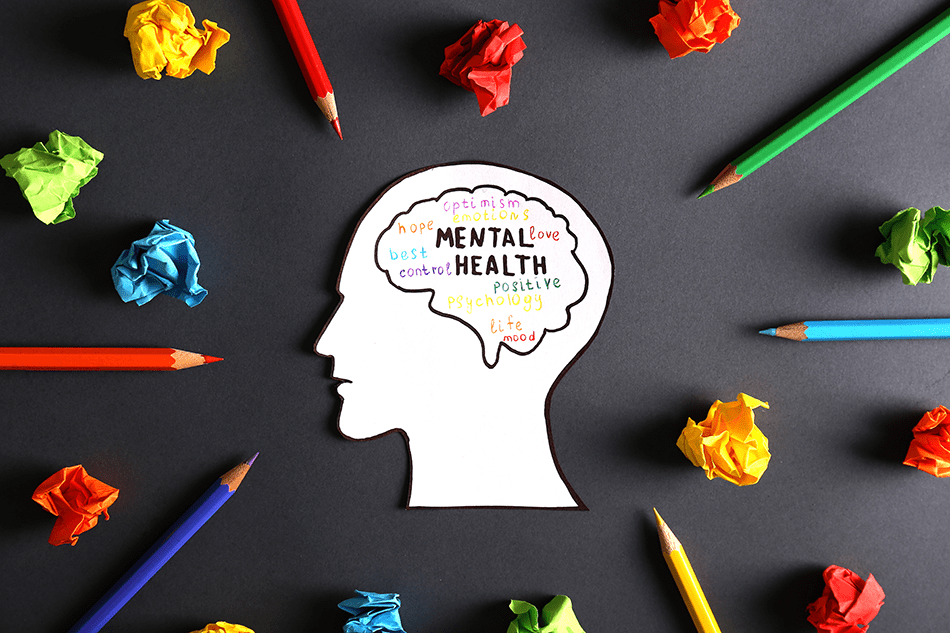
メンタルヘルスケアは、すべての働く人が健やかに、いきいきと働けるようにするために欠かせません。セルフケアは、メンタルヘルスを維持するうえで欠かせない要素のひとつです。
本記事では、メンタルヘルスのセルフケアとは何か、具体的なリフレッシュ方法について解説します。
メンタルヘルスケアにおけるセルフケアとは
セルフケアとは、厚生労働省が2006年に発行した「労働者の心の健康保持増進のための指針」において、4つのケアのひとつとして位置づけられています。こちらは、各事業場がメンタルヘルス対策を推進することを目的としています。
心を健康に保つためには、メンタルヘルスの不調に自分自身で気づき、適切なケアを行うことが重要です。
4つのケア
労働者の心の健康保持増進のためにはセルフケアのみならず、ほかのケアについても知っておくことが重要です。「労働者の心の健康保持増進のための指針」の4つのケアの詳細は以下の通りです。
セルフケア
自分自身の精神的な健康を守るためのセルフケアは、メンタルヘルスケアの中で重要な役割を果たします。ここでいうセルフケアとは自分自身の心の状態に気づいて、適切に対処することです。
自分にとってのストレスは何かということや、そもそもメンタルヘルスとは何なのかということを知り、正確な知識を基に、ストレスチェックなどを利用して自分にストレスがかかっているのかどうかを把握して、対処することが重要です。
ラインによるケア
ラインによるケアとは、職場の管理監督者が部下の異変にいち早く気づき、ケアをしていくことです。以下のような兆候が見られた時には何かしらの悩みやストレスを感じているかもしれません。
- 遅刻、早退、欠勤が増える
- 無断欠勤
- 職場での会話がない
このような状態が見られた場合、適切な対応を検討することが重要です。また、自分の状態を管理者に報告できる人もいます。部下が相談に来た際には、話をよく聞き、必要に応じて情報を提供し、支援することが大切です。
事業場内産業保健スタッフ等によるケア
各事業場では、産業医、保健師、衛生管理士などの事業内産業保健スタッフが中心となって、メンタルヘルスケアの企画・立案を行います。また、医療機関などの外部資源とネットワークを築き、相談窓口としての役割も担います。
職場復帰における支援も重要な取り組みです。特に、メンタルヘルスの問題を理由に、過去1年間に連続1か月以上休業した労働者の割合は企業規模が大きくなると増える傾向にある一方で、メンタルヘルスの不調で休業した労働者は、職場復帰を難所として捉えています。
厚生労働省では「職場復帰支援の手引き」を発行しているため、参考にしながら職場復帰が円滑に行えるようなプログラムを構築しましょう。
事業場外資源によるケア
事業場外資源とは、医療機関や地域保健機関、従業員支援プログラム(EAP; Employee Assistance Program)機関などのメンタルヘルスケアの専門知識を持つ機関のことです。
これらの機関と職場が連携してケアを行うことで、早期の回復を期待します。また、事業場外の資源を利用することで、労働者のプライバシーが守られ、職場の人にメンタルヘルスの不調の詳細を知られることなくケアを進められるというメリットもあります。
セルフケアが必要な理由
セルフケアが必要とされる背景には、現代社会に多く潜んでいるストレスがあります。多大なストレスの結果として、メンタルヘルスの不調に悩む人は年々増えています。
2021年労働安全衛生調査によると、過去1年間にメンタルヘルス不調により連続1か月以上休業、または退職した労働者がいた事業所の割合は10.1%となりました。つまり、10社に1社がメンタルヘルス不調を理由にした退職者や休業者が出ている計算になります。
出典:令和3年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況(厚生労働省)(2025年3月7日使用)
現代社会においてストレスを完全になくすということは難しいですが、セルフケアをすることでストレスとうまく付き合いながら仕事ができるでしょう。
会社や自宅でできるセルフケアの方法5つ
セルフケアが大切だと分かっていても、具体的な方法が分からない方もいるのではないでしょうか。セルフケアを習慣化するには、コツをつかむことが重要です。ここでは、会社でできるセルフケアと自宅でできるセルフケアに分けて解説します。
会社でできるセルフケアの方法
セルフケアは自宅でゆっくり行うものと思われがちですが、仕事中でも簡単に実践できます。ストレスをため込まず、その都度解消することが、心身の健康を守るうえで重要です。会社でできるセルフケアは次の通りです。
腹式呼吸をする
腹式呼吸は道具や場所を選ばず手軽に行えるため、メンタルヘルスのセルフケアとして取り入れやすい方法です。
ゆっくりと3秒ほどかけて口から息を吐き出し、息を吐き出せたら、同じように3秒かけて鼻からゆっくり息を吸い込みます。これを5~10分ほど繰り返します。
背筋を軽く伸ばして座り、目を閉じてお腹に手を当て、呼吸に意識を向けながら行いましょう。
体を動かす
適度に体を動かすことで、ストレスホルモンの分泌が抑えられ、メンタルヘルスの改善につながることが分かっています。また、血流が促進され、質の良い睡眠をサポートするため、疲労回復効果も期待できます。
運動の種類は、ランニング、ウォーキング、ストレッチなど何でも構いません。大切なのは、無理なく継続することです。
厚生労働省の身体活動ガイドライン「アクティブガイド」では、毎日の運動習慣を推奨しており、「+10(プラステン)」として今より10分多く体を動かすことを勧めています。職場の空き時間を活用して、少しでも多く体を動かすことが大切です。
出典: 身体活動ガイドライン「アクティブガイド」(厚生労働省)(2025年3月7日利用)
例えば、仕事の合間にラジオ体操や軽いストレッチを取り入れる、近くのレストランまで歩いてランチに行くなど、日常の中で自然に体を動かす工夫ができます。無理のない範囲で運動を取り入れ、ストレス対策としてセルフケアを実践していきましょう。
自宅でできるセルフケアの方法
続いては、自宅でできるセルフケア方法をご紹介します。
音楽を聴く
音楽にはメンタルヘルスを整えるセルフケア効果があり、医療現場でも音楽療法として活用されています。
リラックスできる環境で音楽を聴くと、副交感神経が優位になり、血流が促進され、末梢皮膚の温度が上昇すると考えられています。これにより、心身のリラックスが促進される効果が期待できます。
気持ちを紙に書いてみる
もやもやとした気持ちや苦しい気持ちは頭で考え込むのではなく紙に書きだしてみましょう。紙に書きだすことで自身の考えを客観的に見られるようになるほか、文字にすることで新たな発見や気付きを得られるかもしれません。
なりたい自分について考える
ストレスを抱えて悩んでいると、自分の欠点や弱さばかりが気になりがちです。そんなときこそ、「なりたい自分」を意識してみましょう。理想の自分を思い描き、それに近づくための小さな目標を設定して取り組んでいくことで、自信を取り戻すことができます。
まずは、無理なく達成できる目標を立て、少しずつ積み重ねていきましょう。そうすることで、心のバランスを整え、前向きな気持ちを取り戻すことができます。
フェムテックを活用したセルフケア
女性においてはフェムテックの活用がセルフケアにもつながります。女性のストレスや気分の浮き沈みには女性ホルモンが関係していることもあります。
基礎体温や排卵日を予測するアプリを利用して自分のホルモンバランスを知り、メンタルが落ち込むタイミングを知って早めにセルフケアに講じるとよいでしょう。また、ホルモンバランスを安定させたいという方は、婦人科等を受診して、低用量ピルなどの処方が可能か相談することもおすすめです。
まとめ
メンタルヘルスのセルフケアは、働く人々が健やかに過ごすために欠かせません。ストレスは完全に避けられないため、適切にセルフケアを行いながら心身の健康を維持することが重要です。
セルフケアにはさまざまな方法があります。また、女性のメンタルケアにはフェムテックの活用も有効です。セルフケアを習慣化し、日常生活の中でストレスとうまく付き合いながら、健康的に過ごしましょう。
監修者

大迫 鑑顕
千葉大学大学院医学研究院精神医学 特任助教
Bellvitge University Hospital, Barcelona, Spain
医学博士、精神保健指定医、日本精神神経学会認定精神科専門医・指導医、日本医師会認定産業医、公認心理師
あすか製薬 フェムナレッジでは、女性従業員の活躍を推進するサービスを導入したい企業の皆さまや今後女性特有の健康課題に関する取り組みを検討されている企業の皆さま向けに動画研修サービスをご提供しております。
Mint+ フェムナレッジについての
お問い合わせはこちらから


