- TOP
- 企業向けColumn
- 生理痛だけじゃない 月経サイクルの中間期に起こる「排卵痛」とは
生理痛だけじゃない 月経サイクルの中間期に起こる「排卵痛」とは

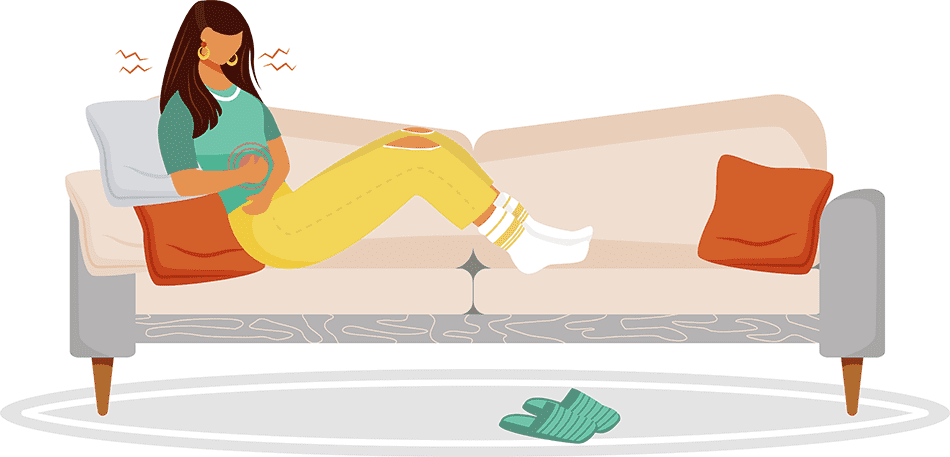
月経から2週間前頃にみられる排卵痛。生理痛(月経痛)よりも頻度が少ないことから、排卵痛は理解されにくい特徴があります。
本記事では排卵痛が起こる仕組みや症状、注意したい病気について解説します。記事を読むことで、企業が活用できる排卵痛に対するフェムテックについても知ることができます。
「排卵痛」とは?なぜ起こる?
排卵痛とは、排卵期に起こる下腹部の痛みのことです。排卵が起こると、卵巣から卵子が排出されて、少量の液体や出血がお腹に流れます。
流出した液体や出血が腹膜を刺激して排卵痛が生じるとされています。他にも、排卵期の卵管の収縮が原因と言われています。
月経周期と関連する排卵メカニズム
排卵は月経周期の中間に起こるものです。月経周期には大きく分けて「卵胞期」「排卵期」「黄体期」「月経期」の4つの周期があります。生理が規則的な人であれば、前回の月経から2週間前が排卵期に当たります。
卵巣内には休眠状態の「原始卵胞」があり、さまざまなホルモンの影響を受けて、2週間かけて成熟していきます。この間、卵胞からはエストロゲン(卵胞ホルモン)が分泌されています。卵胞が成熟すると、脳から指令が来て、卵胞が破れ卵巣から卵子が排出されます(排卵)。排卵後に残った卵胞は黄体となり、「プロゲステロン(黄体ホルモン)」とエストロゲンを分泌します。
排卵痛の症状とは
排卵痛はおなかにチクッとした痛みや、引きつれとして感じることが多いようです。痛みは、排卵出血により血液がお腹に流れることで起こるものであり、卵巣からの卵子排出によるものではありません。
排卵痛の持続時間は数時間から1~2日間で、その後自然に治まることがほとんどです。痛みが出現する部位には個人差があり、毎回同じ場所が痛む人、毎月左右交互に痛む人、下腹部全体が痛む人がいます。多くの場合、排卵痛は軽いですが、お腹に流れる出血量によっては強い痛みを感じる人もいます。
なお排卵痛とともに、排卵出血(中間期出血)がみられる人もいます。排卵期はホルモンバランスが変化する時期であり、体の不調を感じる人も少なくありません。
排卵痛の改善方法
排卵痛を改善するには、痛み止めを飲む方法があります。痛み止めは「プロスタグランジン」という痛みを強める物質の発生を抑える薬です。そのため、排卵痛が強くなる前に飲むのが適しています。
毎月排卵痛で悩まされている人は、低用量ピルにより痛みの改善が期待できるでしょう。低用量ピルは、排卵を抑制する働きがあります。低用量ピルを飲むことで、排卵痛を和らげる効果も期待できます。
排卵痛って普通?病気との違いをチェック!
強い排卵痛がみられる場合、他の病気が潜んでいる可能性があります。ここからは、排卵痛と間違えやすい病気について紹介します。
排卵痛の裏に潜む女性特有の病気とは?
排卵期に強い痛みがみられる場合、排卵そのものではなく病気が原因になっている可能性があります。排卵痛と関連した女性特有の病気には、次のものあります。
子宮内膜症
子宮内膜症により、強い排卵痛が起こることがあります。子宮内膜症とは、子宮以外の場所に子宮内膜の細胞や組織が増殖する病態です。子宮内膜は妊娠と深い関わりがあり、月経周期にともない形態が変化します。子宮内膜症により炎症や癒着があると、排卵期に強い痛みが生じます。
卵巣嚢腫(らんそうのうしゅ)
卵巣嚢腫により排卵痛が強くなることもあります。卵巣嚢腫とは、卵巣内の袋に液体や脂肪がたまる病態のことです。排卵の成熟が妨げられ、排卵期に痛みを生じることがあります。卵巣嚢腫が小さいうちは経過観察となりますが、大きさが4~6㎝になると、ねじれや破裂のリスクがあるため手術が検討されます。
その他
排卵期にみられるお腹の痛みには、排卵そのものではなく、排卵期のホルモンバランスの影響によって起こるものもあります。例えば、排卵期には女性ホルモンの「エストロゲン」の分泌が増え子宮の収縮がみられます。これにより、排卵期にけいれんのような痛みが生じることがあります。
また、エストロゲンには静脈を広げる作用もあり、骨盤内にうっ血が起こると痛みの原因になります。
こんな症状に注意!早めの婦人科受診を
排卵痛は自然にみられるものであり、病気ではありません。ほとんどの場合、排卵痛は強い痛みではなく、排卵期を過ぎれば痛みは自然に治まります。痛み止めを飲んでいても、排卵痛のコントロールが不良な人は、女性特有の病気が隠れているかもしれません。原因を詳しく調べるために、早めに婦人科を受診しましょう。
「生産性の低下」が懸念される排卵痛
排卵痛をはじめ、月経周期にともなう女性の体調の変化は、仕事のパフォーマンスに影響を与えるものです。生理による体調不良は、一人で我慢してしまう女性は多くいます。企業が排卵痛に対して理解を深め、周りからフォローを受けられるような体制づくりを整えることが大切です。
認知されにくい・・・生理(月経)痛に隠れた排卵痛
近年、生理痛(月経痛)やPMS(月経前症候群)について知る男性が増えています。そんななか、見逃されやすい生理(月経)周期にまつわる健康トラブルのひとつが排卵痛です。当社が行ったアンケート調査によると、排卵痛のように生理(月経)期以外の症状について知る男性の割合は4割弱でした。
とくに排卵痛は頻度が少なく、女性の20~40%にみられるといわれています。女性の8割にみられる生理痛と比べると、性別に関わりなく認知が進みにくい状況にあるといえます。
働く女性が感じる排卵痛の悩み
働く女性のなかには、排卵痛により仕事に支障をきたしている人もいます。排卵痛がみられる女性の割合はそれほど高くないため、同性からも理解を得るのが難しいものです。
また概して排卵痛は“軽い痛み”と評価されがちです。実際には、排卵時の出血量や婦人科系疾患の有無などによって痛みの程度が大きく異なります。そのため、強い排卵痛がみられる女性のなかには、周囲から理解を得られず一人で無理してしまう人もいるでしょう。
企業・従業員の理解を高めるために
女性の排卵痛の理解を深めるには、生理(月経)に関する啓蒙活動のなかで排卵痛に関しても触れる必要があります。とくに生理(月経)に関する企業研修をする際、生理(月経)前や生理(月経)中に内容がフォーカスされる傾向があります。排卵痛に関しても、排卵痛で苦しんでいる女性がいること、強い排卵痛には婦人疾患が潜んでいることがあること等、研修内容で触れると社員の理解を深めるきっかけになるでしょう。
女性の健康課題に向き合う「フェムテック」の導入で働く女性をサポート
排卵痛をはじめ女性特有の健康課題をサポートする方法として「フェムテック」があります。フェムテックとは、女性の健康の悩みの解決を目指したテクノロジーの用いた製品・サービスのことです。
排卵日を把握して排卵痛の事前対策を
毎月排卵痛で困っている女性は、排卵日予測アプリを使用してみるのもよいでしょう。排卵アプリは妊活のためだけでなく、排卵日を知るのにも役立ちます。排卵痛が起こりやすいタイミングを知ることで、体調への配慮や安心感につながります。
また排卵痛に関するフェムテックには、医師への相談や低用量ピルの処方をオンラインで受けられるものもあり、仕事が忙しい女性にも適しています。
働く女性をフェムテックでサポートしよう
企業側は女性社員の一人一人の月経周期まで知る必要ありません。ただ排卵痛のような体の不調がみられたときに、仕事のサポートを受けられたり、早退や休暇を選択できたりする職場環境を作っていくことが大切です。
性別に関わりなく、排卵痛といったホルモンバランスの変化にともなう女性の健康課題への理解を深めつつ、業務を協働して行う体制も整えていきましょう。
まとめ
排卵痛は、主に排卵出血により血液がお腹の中で流れることによって起こる刺激痛です。痛みの程度は個人差があり、出血量や疾患の有無により、薬で上手くコントロールできないことがあります。
排卵痛は頻度が少ないことから、男性だけでなく女性側の理解が乏しいことも少なくありません。すべての女性社員の活躍推進を図るために、フェムテックを導入して排卵痛のある女性のきめ細やかなケアを行っていきましょう。
監修者
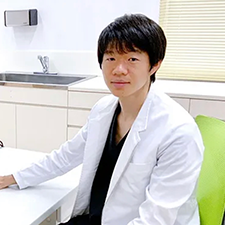
馬場 敦志
筑波大学医学専門学類卒業し、現在は札幌市の宮の沢スマイルレディースクリニック院長を務める。産婦人科専門医の資格を持つ。
あすか製薬 フェムナレッジでは、女性従業員の活躍を推進するサービスを導入したい企業の皆さまや今後女性特有の健康課題に関する取り組みを検討されている企業の皆さま向けに動画研修サービスをご提供しております。
Mint+ フェムナレッジについての
お問い合わせはこちらから


