- TOP
- 企業向けColumn
- 女性が「管理職になりたい!」と思える会社に 女性管理職を増やす方法とは?
女性が「管理職になりたい!」と思える会社に 女性管理職を増やす方法とは?

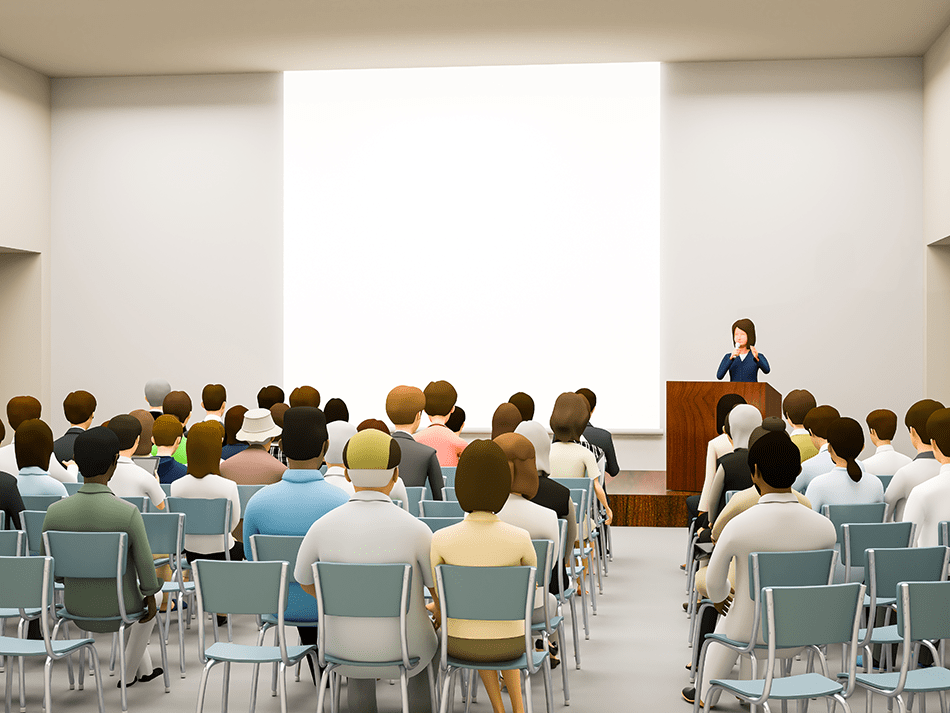
日本の女性管理職の割合は、政府が2030年までに諸外国と近い水準にまで増やすことを目標に掲げているものの、依然として低いのが現状です。女性管理職の増加は、企業の成長や従業員のモチベーション向上に寄与すると考えられています。
この記事では、女性管理職が増えない要因や、増やすための施策についてご紹介します。
日本の女性管理職の現状
冒頭でも述べた通り、日本における女性管理職の割合は、上昇傾向ではあるものの、依然として低水準です。内閣府が発表している2021年のデータによると、日本の企業における女性管理職の割合は13.2%ですが、アメリカやフランス、イギリス、ノルウェーといった欧米諸国では30%以上と、大きく差がついています。
出典: 1-18図 諸外国の就業者及び管理的職業従事者に占める女性の割合(男女共同参画局)(2025年2月16日利用)
また、上場企業の役員に占める女性の割合も、欧米諸国では30%以上である一方、日本では13.4%にとどまっています。日本では「女性が男性と同じだけのキャリアを積めている」とは言い難いのが現状です。
政府の目標
政府は「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2024」において、東証プライム市場の上場企業役員に占める女性の割合を、2025年までに19%・2030年までに30%とする目標が掲げられました。管理職や役員に女性を登用する取り組みを進め、目標を達成するには、課題が残っています。
なぜ女性管理職を増やすのか
女性管理職を増やす必要性やそのメリットについて、ご紹介します。
女性管理職の必要性
近年は、組織の競争力を高め、持続可能な成長をしていくために、ダイバーシティ経営が求められるようになってきました。その一環として、女性管理職の増加は欠かせません。管理職や役員が多様な視点を持つことで、新たなアイデアが生まれやすくなり、より柔軟な意思決定が可能になるためです。
また、女性の管理職登用は、企業の社会的評価を高める要素にもなります。実際、女性役員比率が30%以上の企業は、30%未満の企業よりも投資家等から高い評価が得られたと報告されています。
さらに、女性管理職の増加は、企業文化の変革にもつながります。従来の固定的な労働環境を見直し、柔軟な働き方を取り入れることで、より多様な人材が活躍できる組織となるでしょう。これにより、企業全体の生産性向上が期待されます。
出典:令和5年度女性登用の加速化に向けた取り組み事例集(男女共同参画局)(2025年2月16日利用)
女性が管理職になるメリット
女性が管理職に就くことで、組織全体の働き方改革が進みやすくなります。例えば、ワークライフバランスを考慮した柔軟な働き方の推進や、女性社員のキャリア形成支援が強化されることで、より多様な人材の活躍が可能になるでしょう。
「管理職になってよかった」と感じた女性は7割
株式会社Mentor Forの調査によると、女性管理職のうち約70%が「管理職になってよかった」と感じているという結果でした。その理由として、「やりがいが生まれた」「自身の成長につながった」などが上位に挙げられています。
出典:【女性管理職の意識調査】管理職になることへのマイナスイメージは着任後にポジティブな体験に変化傾向(PR TIMES)(2025年2月16日利用)
女性上司がいるとモチベーションが高くなる!?
JTBコミュニケーションデザインが実施したアンケート調査によると、女性管理職比率が3割以上の会社では、男性のモチベーションが高くなっているという結果が出ています。
また、女性管理職のもとで働く部下は、男性管理職のもとで働く部下と比べて、「今の仕事に喜びを感じる」と回答する人の割合が高いこともわかりました。
出典:~女性管理職の実像と本音~ vol.2「女性管理職の本音とマネジメント行動に関する調査」(JTBコミュニケーションデザイン)(2025年2月16日利用)
女性管理職が増えない要因・課題とは
女性管理職が増えない背景には、女性自身の要因も隠れています。
女性自身が望まない
女性管理職が増えない要因の一つとして、管理職になることを望んでいない女性も多いというのが現実です。健康上の問題がない男性は、40〜60%が昇進を希望しています。一方、女性は「今より上の役職に就きたい」と考える傾向が全体的に低く、健康上の問題がない方でも、昇進の希望があるのは20〜30%という結果でした。
家庭と両立が難しい、業務負担が増えるといった懸念から、管理職を希望しない傾向があると指摘されています。また、企業文化や労働環境の問題もあり、長時間労働を前提とした働き方のイメージが、女性の昇進意欲を低下させる要因となっています。
出典:男女共同参画白書 令和6年度版 特-62図(男女共同参画局)(2025年2月16日利用)
女性に多いアンコンシャス・バイアス
女性自身も、無意識のうちに性別役割意識に囚われ、自らの可能性を狭めてしまっている可能性があります。
内閣府共同参画局の調査では、以下のような項目について、女性も「そう思う傾向」が強いという結果でした。
- 育児期間中の女性は重要な仕事を担当すべきでない(33.2%)
- 組織のリーダーは男性の方が向いている(20.9%)
- 家事・育児は女性がすべきだ(20.7%)
- 受付、接客・応対は女性の仕事だ(18.3%)
一方で、実際には上司に女性のいる環境の方が、「人間関係が良い」「アイデアを提案しやすい」等ポジティブな風土であるという意見が多く、女性が管理職に向いていないということはありません。
企業には、女性自身のアンコンシャス・バイアスを取り除き、積極的にキャリアアップを目指せる環境作りが求められるでしょう。
出典:令和4年度 性別による無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)に関する調査研究(内閣府男女共同参画局)(2025年2月16日利用)
女性管理職を増やすために企業で考えることとは
女性が管理職を目指せる職場を作るためには、企業の力が必要不可欠です。
女性が「管理職になりたい!」と思える職場作りとは
女性が管理職を目指すためには、まず「働きやすさ」と「成長の機会」が確保されていることが重要です。たとえば、妊娠・出産後もスムーズに復職できるようなサポート体制の確立や、リモートワーク・フレックスタイム制度の活用が挙げられます。家庭と仕事を両立しやすい環境を整えることで、管理職を目指すことが選択肢になる女性が増えるでしょう。
また、先ほど紹介したアンコンシャス・バイアスを解消できるような、社内風土の醸成も不可欠です。女性管理職育成研修、メンター制度のような女性に向けた取り組みのほか、男性も含めてジェンダー平等について理解を深めていくための研修なども必要になるでしょう。
女性の健康課題に耳を傾ける必要性
女性には、各年齢層で生理(月経)・妊活(不妊治療)・更年期症状など、さまざまな健康課題が生じます。厚生労働省の調査によると、仕事と不妊治療の両立ができずに、16%の方が離職しているそうです。
出典:仕事と不妊治療の 両立支援のために(厚生労働省)(2025年2月16日利用)
女性特有の健康問題から目を背けず、うまく対処しながら働き続けやすい環境づくりをしていく必要があります。
そこで、「フェムテック」の活用がおすすめです。フェムテックは、女性特有の健康課題をテクノロジーで解決するサービスや商品を指します。たとえば、オンライン健康相談サービスや女性専用の予防医療サービスの導入などを検討してみてはいかがでしょうか?
まとめ
今回は、日本で女性管理職が増えない要因について掘り下げるとともに、女性管理職を増やすために必要な企業の取り組みについてご紹介しました。女性管理職が増えることは、企業にとっても大きなメリットとなります。女性活躍のための取り組みの一環として、フェムテックの活用もご検討ください。
監修者

大迫 鑑顕
千葉大学大学院医学研究院精神医学 特任助教
Bellvitge University Hospital, Barcelona, Spain
医学博士、精神保健指定医、日本精神神経学会認定精神科専門医・指導医、日本医師会認定産業医、公認心理師
あすか製薬 フェムナレッジでは、女性従業員の活躍を推進するサービスを導入したい企業の皆さまや今後女性特有の健康課題に関する取り組みを検討されている企業の皆さま向けに動画研修サービスをご提供しております。
Mint+ フェムナレッジについての
お問い合わせはこちらから


