- TOP
- 企業向けColumn
- 従業員の健康が企業の未来をつくる 福利厚生における健康支援の重要性
従業員の健康が企業の未来をつくる 福利厚生における健康支援の重要性

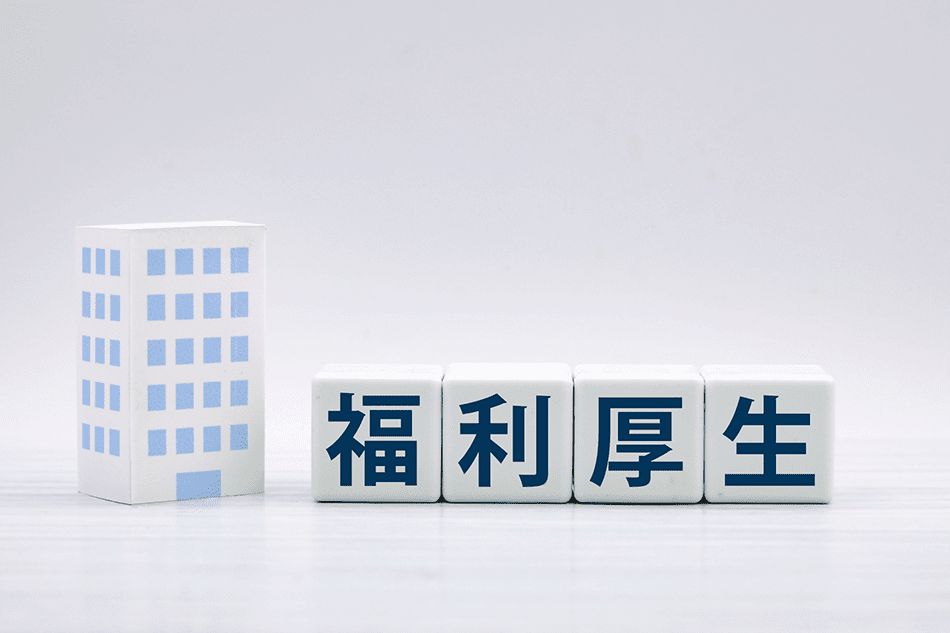
近年、企業の成長には「健康経営」の視点が不可欠とされており、福利厚生の重要な要素となっています。特に、女性特有の健康課題への対応は、ダイバーシティ推進や働きやすい環境づくりの観点からも重要です。
生理痛や更年期障害、不妊治療などの課題に対し、フェムテックを活用したサポートも進んでいます。この記事では、福利厚生における健康支援の重要性を解説し、具体的な施策やフェムテックの活用方法について紹介します。
福利厚生における健康支援の重要性
福利厚生として従業員の健康維持・増進をはかることは、従業員個人にとってだけでなく、企業にとっても有益なことです。具体的に解説します。
従業員の健康が業務効率に与える影響
従業員の健康状態は、企業の生産性や業績に直接的な影響を与えます。
健康投資に関して、世界中の250社を対象にした調査があります。その結果、生産性やモチベーションの向上、リクルート効果、医療コストの削減など、3倍のリターンが得られることがわかりました。
出典:健康経営の推進について(経済産業省)(2025年3月7日使用)
健康状態が良い会社では、従業員のパフォーマンスが向上し、離職率が低下する傾向があります。そのため、企業が従業員の健康維持・増進に投資することは、長期的な競争力強化につながります。
さらに、就職を考える際に職場に求める条件として、「心身の健康を保ちながら働けること」を挙げる人も多いです。求職者に対して、従業員の健康維持のための福利厚生があるとアピールできれば、人材獲得にも有効と考えられます。
出典:健康経営のメリット(ACTION!健康経営)(2025年3月7日使用)
健康経営優良法人制度とは
「健康に配慮した企業である」とアピールする1つの方法として、健康経営優良法人制度があります。健康経営優良法人制度とは、経済産業省が主導する制度で、健康経営を推進する企業を認定するものです。
この認定を受けることで、企業は社会的な評価を高め、優秀な人材の確保や従業員のモチベーション向上を狙うことができます。また、自治体や金融機関から、減免措置や融資、表彰などのインセンティブを受けることも可能です。
認定には、以下のような項目が評価されます。
- 経営理念や方針
- 健康づくり担当者の設置
- 従業員の健康診断受診率
- ヘルスリテラシー向上のための教育制度
- 私病等に対する両立支援
- 健康保持や増進のための取り組み
2024年度の段階で、約2万の法人が健康経営優良法人として認定されました。健康経営優良法人の認定を通して、選ばれる企業、価値のある企業を目指しましょう。
福利厚生における健康支援制度の主な種類
前提として、福利厚生には「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の2つがあります。法定福利厚生に含まれるのは、健康保険・厚生年金保険、雇用保険、介護保険、労災保険、子ども・子育て拠出金です。企業が法律に基づき負担する義務があります。一方で、法定外福利厚生は、要件や内容が原則自由です。
健康支援は、法定福利厚生の枠組みの中でも行われますが、より手厚いサポートを提供するために、多くの企業が法定外福利厚生を活用しています。例えば、健康診断の充実やメンタルヘルスケアの支援制度、運動習慣の促進、女性特有の健康課題への支援などが挙げられます。
ここからは健康支援制度の代表例をご紹介しますので、各企業の従業員のニーズに合いそうなものがあれば、参考にしてください。
健康診断に関する制度
健康診断の充実は、従業員の満足度向上につながります。
法定健診の実施
企業には労働安全衛生法に基づき、定期的な健康診断の実施が義務付けられています。従業員の健康状態を把握し、生活習慣病や職業に関連した疾患の早期発見・早期治療を促すことが目的です。
オプション検査や人間ドックの補助
法定健診に加え、がん検診や生活習慣病検査などのオプション検査を推奨し、企業が費用補助を行うケースも増えています。がんなどの法定検診では見つけにくい疾患を早期発見でき、生産性の向上や、個々人の満足度向上を図ることが可能です。
メンタルヘルスケア支援制度
ストレスチェック制度の導入やカウンセリングサービスの提供など、メンタルヘルスケアの支援は、精神的な健康の維持・向上のために重要です。実際、令和4年の厚生労働省の調査では、精神的な不調が原因で1か月以上の休職をした従業員がいる事業所は約10%で、退職した従業員がいる事業所は約6%にものぼると報告されています。
専門のカウンセラーを配置するなど、従業員が気軽に相談できる体制を整えることで、メンタルヘルス問題の早期対策を図っている企業もあります。
出典:令和6年版 厚生労働白書-こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に(厚生労働省)(2025年3月7日使用)
運動習慣を促進する制度
フィットネスクラブの法人契約やウォーキングイベントの実施など、運動習慣を促進する取り組みが増えています。これにより、従業員の健康維持や生活習慣病などの予防効果が期待できるでしょう。
また、社内でのイベントは、従業員同士のコミュニケーションの促進にも効果的です。
健康的な食生活をサポートする制度
食事補助は、社内食堂での健康メニューの提供や、外部の配送サービスを活用した弁当の提供など、従業員の食事代金の一部またはすべてを企業が負担する福利厚生です。従業員の金銭的な負担軽減のほか、栄養バランス・カロリー等を考慮した食事を提供することが直接的に健康増進へ繋がります。
柔軟な働き方を支援する制度
リモートワークの推進やフレックスタイム制の導入も、働き方改革を通じた健康支援です。従業員の体調に合わせて働き方を調整できれば、精神的・身体的な負担軽減につながるほか、ワークライフバランスの改善にも寄与します。
禁煙・生活習慣改善プログラム
禁煙支援プログラムや健康指導の提供など、生活習慣の改善をサポートする施策も重要です。これにより、長期的な健康リスクを低減し、医療費削減にもつながります。
実際に、「禁煙に成功したら、禁煙外来での治療費を一部負担する」「タバコを吸わない社員へ手当を出す」といった施策を実施し、喫煙率を下げている企業も出てきています。
女性の健康支援(フェムテックの活用)
男性にはない「女性特有の健康課題」にスポットを当てた健康支援も重要です。
女性の健康支援とフェムテックの重要性
女性特有の健康課題である生理痛(月経痛)、更年期症状、不妊治療などは、各ライフステージで関わるものです。パフォーマンスが低下したり、通院のための休暇取得が必要になったりと、人それぞれ必要な支援も異なります。
その解決策として、フェムテック(FemTech)が注目されるようになってきました。生理管理アプリや更年期対策デバイス、不妊治療サポートツールなどの活用で、女性特有の不調にうまく対処できるようになるかもしれません。
企業がフェムテックを導入するメリット
フェムテックの導入により、女性従業員の健康維持やパフォーマンス向上が可能です。その結果、女性がキャリアを継続しやすくなり、企業のダイバーシティ推進や人材確保にもつながります。
企業が女性の健康を重視する姿勢を持つことで、女性の離職率が下がる、女性の管理職割合が高くなるなど、女性従業員のモチベーション向上も期待できます。
まとめ
福利厚生における健康支援は、従業員の働きやすさを向上させるだけでなく、企業の成長にも大きく貢献します。特に、女性特有の健康課題に対応する施策は、離職率の低下や人材確保、企業イメージの向上につながります。健康診断やメンタルヘルスケア、柔軟な働き方の支援に加え、フェムテックの活用などもご検討ください。
従業員の健康を守ることで、より魅力的な職場環境の実現が期待できます。
監修者

大迫 鑑顕
千葉大学大学院医学研究院精神医学 特任助教
Bellvitge University Hospital, Barcelona, Spain
医学博士、精神保健指定医、日本精神神経学会認定精神科専門医・指導医、日本医師会認定産業医、公認心理師
あすか製薬 フェムナレッジでは、女性従業員の活躍を推進するサービスを導入したい企業の皆さまや今後女性特有の健康課題に関する取り組みを検討されている企業の皆さま向けに動画研修サービスをご提供しております。
Mint+ フェムナレッジについての
お問い合わせはこちらから


