母乳はママの免疫物質が含まれるため、赤ちゃんの病気を予防する効果があります。
母乳が出ないようでもあせらずに根気よく吸わせてみましょう。
一方、母乳に近く、赤ちゃんの成長に必要な栄養バランスの粉・キューブ・液体のミルクもあります。
ママの体質や健康状態などによって母乳を与えられないときは、無理せずミルクを活用しましょう。
赤ちゃんの成長と
育児のポイント
待ちに待った赤ちゃんが誕生し、同時に育児もスタート。
「赤ちゃんって、どんな風に成長するの?」
「どんなことに気をつければいいの?」など、
子どもの成長や育児に不安を感じるママやパートナーもいると思います。
今回は、0歳の赤ちゃん~6歳頃までの子どもの成長と育児のポイントを中心に、
知ってもらいたいことをまとめました。
子どもの成長や発達は個人差も大きいため、
ここでご紹介するのはおおよその目安と考えましょう。
多少早くても、遅くても心配はいりません。
赤ちゃんの育ちを見守ることが不安やイライラではなく
安らぎや喜びをもたらすような育児が大切です。
新生児(生後約4週間まで)
母乳やミルクを飲むとき以外は眠っていることが多い新生児。
眠りに入る前のまどろんだ状態や浅い眠りのときに口角を上げてほほえんだり、授乳や入浴の後、あやされているときなどに目の前の顔などをじっと見つめたりします。
そのような「快」の感情に加えて、お腹がすいたり眠いとき、おむつが濡れたときなどには泣くことで「不快」の感情も表現します。
清潔で快適な環境を用意する
新生児のからだは未熟で抵抗力が弱いため、清潔で快適な環境をつくることが大切です。
赤ちゃんのお世話をする前に手を洗い、寝具、衣類、おむつはできる限り清潔な状態に保ちましょう。
一般に新生児は母体や母乳から受けとる免疫力があると言われますが、風邪をひいた場合には、抱っこしたり、同じ部屋に長くいたりすることはできるだけ避けましょう。
また、赤ちゃんは自分で体温を調節することが苦手なため、できれば室温は20℃以下にならないように注意しましょう。
また、安らかな睡眠のために静かな場所に寝かせましょう。
母乳だけでなく粉ミルクなどを
上手に活用

赤ちゃんが泣いてもあわてない
赤ちゃんは泣くことで、「おなかがすいた」、「おむつが汚れて気持ち悪い」、「抱っこしてほしい」などと伝えてきます。
なぜ泣いているのか想像し対応してみてください。
それでも赤ちゃんが泣きやまなければ、ママも泣きたくなるかもしれませんね。
でも、そのようなときは深呼吸をするなど、気分転換してみてはいかがですか。
そうこうするうちに赤ちゃんも泣き疲れて眠ってしまうかも知れません。
赤ちゃんを激しく揺さぶらないで!
赤ちゃんは首が不安定で頭を支えられないため、激しく揺さぶられると、脳が傷つき、重い障害を負うことや、場合によっては命を落とすこともあります。
虐待と誤解されないためにも、どんな状況であれ、赤ちゃんを激しく揺さぶることのないように気をつけましょう。
もしも激しく揺さぶってしまい、その後、目線があわない、ぐったりしているなど赤ちゃんの様子がいつもと違う場合は、すぐに医療機関を受診し、医師にそのことを伝えてください。
- *厚生労働省 動画チャンネルDVD動画『赤ちゃんが泣きやまない』
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000030718.html
「何かおかしい」と感じたら
速やかに受診
母乳・ミルクをいつもより飲まない、熱っぽくて元気がない、顔色が悪い、苦しそうなど、「何かおかしい」と感じたら、速やかに医療機関を受診しましょう。
過剰に神経質になる必要はありませんが、日頃お世話をしているママの「おかしい」は当たっていることも珍しくありません。
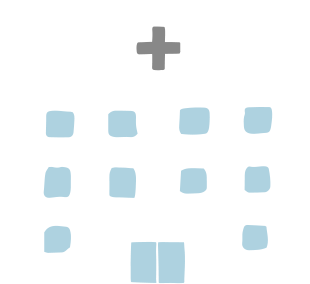
職場復帰を目指すなら
早めに保育施設を確保
「早く職場復帰したいけど預けるならどこがいいの?」、「保育園と幼稚園、どっちがいいの?」、「保育園にはどんな種類があるの?」など、保育施設に関して疑問や不安のあるママは少なくないと思います。
育休中にお住いの市区町村の保育施設の特徴と待機児童の状況などを調べ、早めに準備を進めましょう。
保育園と幼稚園の違い
| 保育園 | 幼稚園 | |
|---|---|---|
| 目的 | 保護者の就労などを理由として、保護者の代わりに乳児または幼児を保育すること | 学校教育の基礎となる「学びに向かう姿勢」を育むために、子ども達が「遊び」を通してさまざまな経験を積み重ねていくこと |
| 対象 | 0歳〜小学校入学前までの乳児や幼児 | 満3歳〜小学校入学前の幼児 |
| 年間保育日数 (子どもを預かって保育を行う日数) |
保育日数に規定はなく、日曜日と祝日、年末年始以外は原則として開所となるため、年間の保育日数は300日程度 | 「年間で39週以上」と設定 |
| 保育時間 | 一般的に7時半〜18時頃(標準8時間) | 9時〜14時頃まで(標準4時間※延長なしの場合) |
| 長期休業 | 原則なし | 夏休みや春休みなど |
| 目的 | |
|---|---|
| 保育園 | 保護者の就労などを理由として、保護者の代わりに乳児または幼児を保育すること |
| 幼稚園 | 学校教育の基礎となる「学びに向かう姿勢」を育むために、子ども達が「遊び」を通してさまざまな経験を積み重ねていくこと |
| 対象 | |
|---|---|
| 保育園 | 0歳〜小学校入学前までの乳児や幼児 |
| 幼稚園 | 満3歳〜小学校入学前の幼児 |
| 年間保育日数 (子どもを預かって保育を行う日数) |
|
|---|---|
| 保育園 | 保育日数に規定はなく、日曜日と祝日、年末年始以外は原則として開所となるため、年間の保育日数は300日程度 |
| 幼稚園 | 「年間で39週以上」と設定 |
| 保育時間 | |
|---|---|
| 保育園 | 一般的に7時半〜18時頃(標準8時間) |
| 幼稚園 | 9時〜14時頃まで (標準4時間※延長なしの場合) |
| 長期休業 | |
|---|---|
| 保育園 | 原則なし |
| 幼稚園 | 夏休みや春休みなど |
認可保育園と認可外保育園の違い
| 認可保育園 | 認可外保育園 | |
|---|---|---|
| 設置基準 | 厚生労働省が定める保育士の人数、施設の広さ、設備など(自治体により異なる) | 厚生労働省が定める基準は満たしていない(自治体が定めた要綱に基づいて運営) |
| 申し込み先 | 自治体 | 施設へ直接 |
| メリット | 保育料の無償化 | 夜間保育や長時間保育などが可能な施設もある |
| 設置基準 | |
|---|---|
| 認可 保育園 |
厚生労働省が定める保育士の人数、施設の広さ、設備など(自治体により異なる) |
| 認可外 保育園 |
厚生労働省が定める基準は満たしていない(自治体が定めた要綱に基づいて運営) |
| 申し込み先 | |
|---|---|
| 認可 保育園 |
自治体 |
| 認可外 保育園 |
施設へ直接 |
| メリット | |
|---|---|
| 認可 保育園 |
保育料の無償化 |
| 認可外 保育園 |
夜間保育や長時間保育などが可能な施設もある |
認定こども園とは?
認定こども園は、親が働いている家庭の子ども(0歳〜小学校入学前まで)だけでなく、親が働いていていない家庭の子ども(3歳以上)も通える保育施設です。
幼保連携型、幼稚園型、保育所型など、さまざまなタイプがあります。
認可保育園に入るには?
まざまな保育施設がありますが、認可施設(認可保育園、認定こども園など)に関しては、市区町村に申し込みます。
入園案内は市区町村のWebサイトからダウンロードできますから、まず現時点での入園案内を入手し、入園手続きなどについて確認しましょう。
可能であれば早い時期に役所の窓口に行き、入園案内の疑問点、希望する園の例年の入園状況などについて聞いてみるとよいでしょう。
ここでは認可保育園に入るための認定申請から入園内定までについて紹介します。
| 保育の必要性の認定申請 | 入園希望月の申請時期に、最新の入園案内(申請用紙)を取り寄せ、申請書類に保育を必要とする事実(家族の就労状況など)について記入し、就労証明や所得証明(源泉徴集票・確定申告の控えなど)を添えて申請 |
|---|
| 保育の必要性の認定申請 |
|---|
| 入園希望月の申請時期に、最新の入園案内(申請用紙)を取り寄せ、申請書類に保育を必要とする事実(家族の就労状況など)について記入し、就労証明や所得証明(源泉徴集票・確定申告の控えなど)を添えて申請 |
| 入園申し込み | 希望する保育園の希望順位を記入(「保育の必要性の認定申請」とセットになっている)。 |
|---|
| 入園申し込み |
|---|
| 希望する保育園の希望順位を記入(「保育の必要性の認定申請」とセットになっている)。 |
| 入園選考 | 希望者が保育園の定員を上回っている場合は、入園選考が行われる。 保護者の就労時間や家庭の状況によって点数がつけられ、客観的に判断される。 就労時間が長いなど、必要性の高い家庭が優先。 |
|---|
| 入園選考 |
|---|
| 希望者が保育園の定員を上回っている場合は、入園選考が行われる。 保護者の就労時間や家庭の状況によって点数がつけられ、客観的に判断される。 就労時間が長いなど、必要性の高い家庭が優先。 |
| 入園承諾(入園内定) | 4月入園の場合は、10月〜11月に申し込みを受け付け、2月に選考結果が発表されるのが一般的。 |
|---|
| 入園承諾(入園内定) |
|---|
| 4月入園の場合は、10月〜11月に申し込みを受け付け、2月に選考結果が発表されるのが一般的。 |