例えば寝返りをするようになったら、窒息事故を防ぐために近くに柔らかい物を置かない、ハイハイが始まったら階段からの転落に気を付け、床に危険なもの(鋭利な物や不潔な物)を放置しないなど、発達の段階に応じた安全の確保が重要です。
また、常に目の届く範囲で見守るなど、注意を怠らないようにしましょう。
赤ちゃんの成長と
育児のポイント
待ちに待った赤ちゃんが誕生し、同時に育児もスタート。
「赤ちゃんって、どんな風に成長するの?」
「どんなことに気をつければいいの?」など、
子どもの成長や育児に不安を感じるママやパートナーもいると思います。
今回は、0歳の赤ちゃん~6歳頃までの子どもの成長と育児のポイントを中心に、
知ってもらいたいことをまとめました。
子どもの成長や発達は個人差も大きいため、
ここでご紹介するのはおおよその目安と考えましょう。
多少早くても、遅くても心配はいりません。
赤ちゃんの育ちを見守ることが不安やイライラではなく
安らぎや喜びをもたらすような育児が大切です。
乳児期(1歳まで)
生後1か月を過ぎると体がふっくらしてきます。
起きている時間が長くなり、うつぶせにすると頭を持ち上げる、足脚をバタバタ動かすなど動きも活発になります。
2か月頃になると、近くにある動くものを目で追うようになります(追視といいます)。
また、ラトル(ガラガラ)など目の前で動くものに手を伸ばしたりします。
4か月頃までには頚(くび)がすわるため(頸定(けいてい)といいます)、縦抱きでも頭部が安定するようになります。
5か月頃になると寝返りをするようになり、6か月頃には少しの時間なら支えがなくてもおすわりができるようになり、7か月頃にはおすわりも安定してきます。
8か月頃からハイハイが始まり、徐々に上達して移動が素早くなります。
10か月頃にはつかまり立ちが安定し、伝い歩きをするようになり、11か月を過ぎる頃から早い子ではひとりで立つことができるようになります。
運動機能の発達に伴い
事故のリスクも高まる
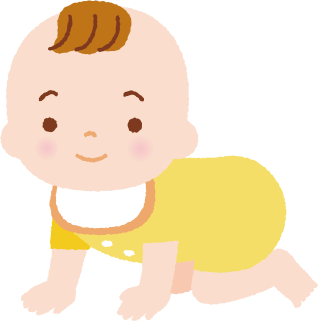
赤ちゃんとの
コミュニケーションを大切に!
言葉がしゃべれない赤ちゃんにとって、泣くことは大事なコミュニケーション手段です。
生後1~2か月頃の赤ちゃんが空腹やおむつの汚れ以外で、泣いたりぐずったりしているときは、抱っこしてあげると良いでしょう。
赤ちゃんは抱っこされると安心して泣きやむことが多いです。
「抱きぐせがつくのでは……」と心配する必要はありません。
言葉が理解できないから無駄と決めつけず、優しい声で語りかけることも大切です。
抱っこしたり、話しかけたり、遊んであげたり、赤ちゃんとのコミュニケーションを大切にしましょう。
生後5か月頃から離乳食を開始
離乳の進め方は、大きく4つの段階(初期、中期、後期、完了期)に分けて考えるとよいでしょう。
| 離乳初期 (生後5〜6か月頃) |
目標 | 口を閉じて離乳食を飲み込めるようになることを目指す。 |
|---|---|---|
| 離乳食の内容 | ペースト状のおかゆ(つぶしがゆ)から始め、すりつぶした野菜なども試し、慣れてきたら、つぶした豆腐や白身魚などを試す。はじめての食材を与える際は、アレルギー症状が出ることも考え、かかりつけの医療機関の診療時間内にする。離乳食を食べさせるのは1日1回を目安とし、母乳や育児用ミルクは、赤ちゃんが欲しがるだけ飲ませる。 | |
| 離乳中期 (生後7〜8か月頃) |
目標 | 徐々に食品の種類を増やす。 |
| 離乳食の内容 | 豆腐程度の硬さのものを舌とあごでつぶして食べることができるようになる。離乳食を与えるのは1日2回を目安とし、母乳は赤ちゃんが欲しがるだけ、育児用ミルクは1日3回くらい飲ませる。 | |
| 離乳後期 (生後9~11か月頃) |
目標 | 手づかみ食べを目指す。 |
| 離乳食の内容 | 触りたい、自分で食べたい、という気持ちが旺盛になる時期。食べ物を前歯で嚙み切って、歯茎を使ってモグモグ食べるようになる。歯茎でつぶせるくらい(例:スティック状のゆで野菜、食べごろのバナナ、豆腐など)の硬さであれば食べることができる。離乳食は1日3回、母乳は欲しがるだけ、育児用ミルクは1日2回程度飲ませる。 | |
| 離乳完了期 (生後12か月~18か月頃) |
目標 | スプーンやフォークを持って自分で食べようとするが、まずは手づかみで食べることにより、自分で食べる楽しさを増やしていくことを目指す。 |
| 離乳食の内容 | 食べ物の硬さは歯茎で噛めるくらいで、手づかみできる大きさのものを取り入れる。離乳食は1日3回、食事の合間におやつ(イモ類や果物など)も加える。母乳は欲しがるだけ、育児用ミルクは食欲や成長に応じて飲ませる。 |
| 離乳初期(生後5~6か月頃) | |
|---|---|
| 目標 | 口を閉じて離乳食を飲み込めるようになることを目指す。 |
| 離乳食 の 内容 |
ペースト状のおかゆ(つぶしがゆ)から始め、すりつぶした野菜なども試し、慣れてきたら、つぶした豆腐や白身魚などを試す。はじめての食材を与える際は、アレルギー症状が出ることも考え、かかりつけの医療機関の診療時間内にする。離乳食を食べさせるのは1日1回を目安とし、母乳や育児用ミルクは、赤ちゃんが欲しがるだけ飲ませる。 |
| 離乳中期(生後7~8か月頃) | |
|---|---|
| 目標 | 徐々に食品の種類を増やす。 |
| 離乳食 の 内容 |
豆腐程度の硬さのものを舌とあごでつぶして食べることができるようになる。離乳食を与えるのは1日2回を目安とし、母乳は赤ちゃんが欲しがるだけ、育児用ミルクは1日3回くらい飲ませる。 |
| 離乳後期(生後9~11か月頃) | |
|---|---|
| 目標 | 手づかみ食べを目指す。 |
| 離乳食 の 内容 |
触りたい、自分で食べたい、という気持ちが旺盛になる時期。食べ物を前歯で嚙み切って、歯茎を使ってモグモグ食べるようになる。歯茎でつぶせるくらい(例:スティック状のゆで野菜、食べごろのバナナ、豆腐など)の硬さであれば食べることができる。離乳食は1日3回、母乳は欲しがるだけ、育児用ミルクは1日2回程度飲ませる。 |
| 離乳完了期(生後12か月~18か月頃) | |
|---|---|
| 目標 | スプーンやフォークを持って自分で食べようとするが、まずは手づかみで食べることにより、自分で食べる楽しさを増やしていくことを目指す。 |
| 離乳食 の 内容 |
食べ物の硬さは歯茎で噛めるくらいで、手づかみできる大きさのものを取り入れる。離乳食は1日3回、食事の合間におやつ(イモ類や果物など)も加える。母乳は欲しがるだけ、育児用ミルクは食欲や成長に応じて飲ませる。 |
生後7か月頃になると
朝まで寝てくれるかも
夜中にたびたび泣いてママやパートナーを寝かせてくれない赤ちゃん。
「いったいいつになったら朝まで寝てくれるの……」と途方にくれることもあるかと思います。
生後7か月頃に離乳食が1日2回になり、しっかり食べられるようになると夜間授乳による栄養が不要になってきます。
つまり、生後7か月頃からは朝まで寝てくれる可能性が出てきます。
赤ちゃんがまとまった時間、続けて寝てくれるようになるためにできることとして、起床時刻と就床時刻を一定にして生活リズムを整える、連続して3時間以上昼寝しているときは優しく声をかけて起こす、寝る前にしっかり授乳し空腹による覚醒を避ける、睡眠環境を安全で快適なものにする(室温、光、音への配慮)などが挙げられます。
発達障害と決めつけないで、
まずは相談を
発達障害とは、物事の捉え方や行動のパターンに強い個性があるため、日常生活、社会生活に支障を生じている状態のことです。
最近では神経発達症と呼ばれることが多いです。
発達障害には、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、限局性学習症(SLD)など、さまざまな種類があります。
ASDには、相手の感情に無関心、興味や関心の対象が限られている、決まった行動を延々と繰り返す、などの特徴があります。
ADHDには、うっかりミスが多い、良く考えずに行動してしまう、落ち着きがないといった特徴があります。
SLDには、全般的な知的能力に遅れはないのに、読む、書く、あるいは計算するなどの能力のうち、いずれかが著しく苦手といった特徴があります。
特別な療育(手助け)が必要とは限りませんが、問題が明らかな場合には、家庭や園で心地よい環境を整えてあげることが役立つこともあります。
例えば、大人の接し方を工夫することによって、子どもが自分に自信(自己肯定感)を持ち、その子が持っている優れた一面を伸ばしていくこともできます。
発達障害の徴候は様々です。乳児期(1歳まで)の場合、「抱っこや手をつなぐことを極端に嫌がる」、「あやしても笑わない」、「寝つきが悪く、寝てもすぐに目を覚ます」などが一例です。
これらの徴候が複数、長く続く場合には、まずは小児科医、小児神経科医、児童精神科医などに相談してみませんか。